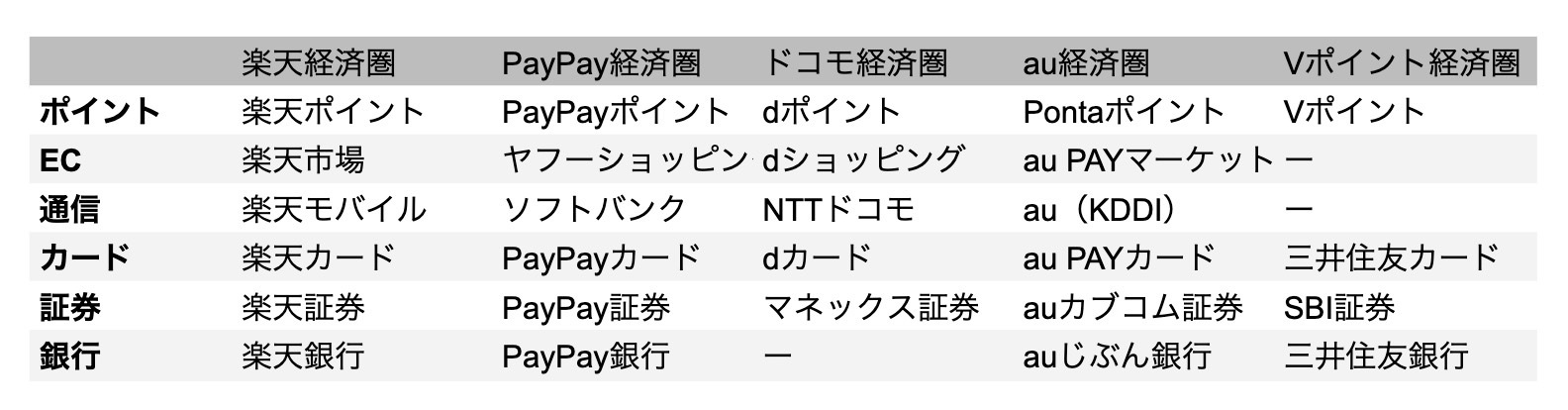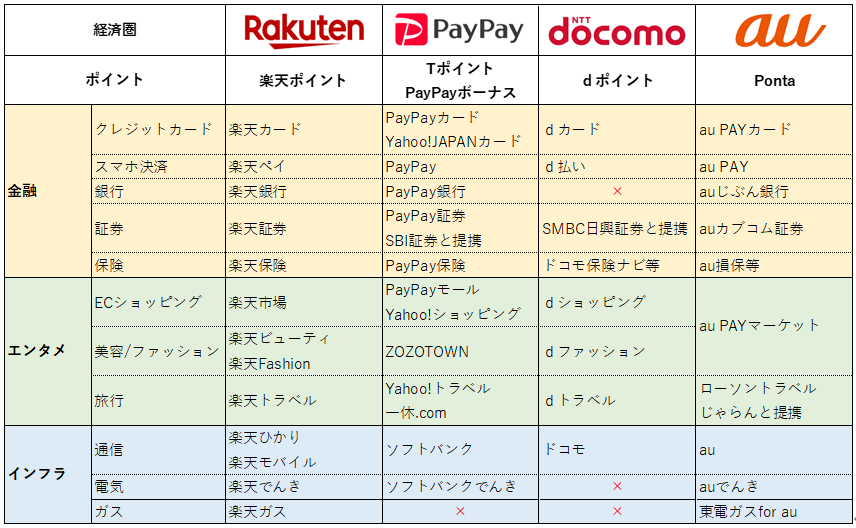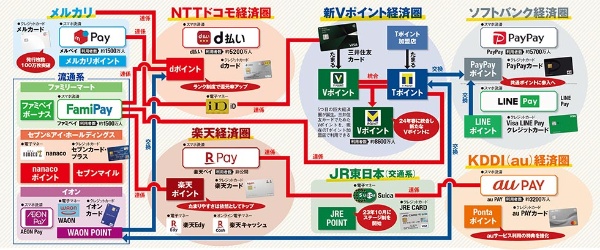マティス 自由なフォルム | 企画展 | 国立新美術館 THE NATIONAL ART CENTER, TOKYO
開催概要
会期
2024年2月14日(水) ~ 2024年5月27日(月)
毎週火曜日休館
※ただし4月30日(火)は開館開館時間
10:00~18:00
※毎週金・土曜日は20:00まで
※4月28日(日)・5月5日(日)は20:00まで
※入場は閉館の30分前まで会場
国立新美術館 企画展示室2E
〒106-8558東京都港区六本木7-22-2
5解説通り大きく見下す構図セザンヌ?
678印象派点描シニャック
随所に巨匠の影響、若干にしてコツを
フォービズムの純色、それ自体は印象派そのものでは?解説に対し
5の影や7の空のグラデーションとかはそうかも
9は彩度抑えめでパステルで好き
白地なのもいい
フォルム系も萌芽?
アンリ・マティス《マティス夫人の肖像》1905年
油彩/カンヴァス、46 × 38 cm、ニース市マティス美術館蔵
© Succession H. Matisse Photo: François Fernandez
10影の色味が特徴的
原色でないものの鮮やかめなモス的グリーンとピンク
色そのものは野獣的でないが、配色は挑戦的
sec2
18本来的な風景画として彩度低めが現実的か
これまでとギャップにも映る
20サイズのズレた額が逆に引き立たせて効果的
21女性のシルエットのエッジが強調され、前章の彫刻も相まって関連性を感じる
作為的な背景!!
不自然さ
32左肩のエッジ影が強調される、近くにあるような圧を感じるような演出効果
肩と同じ方向に釣り上がって傾く顔も効果にシナジーを生んでいる
右太ももも太い
比較的遠いくびれは細く、遠近法の強調、親戚か
赤い家の歪みのしょうや?
33裸婦の肌色とネックレスの紺、
壁紙の薄紫と植物の緑の補色対比が意図的だろう
35配色はまさしくウクライナ
まだテーブルの木の黄色と影の紺として現実性、理性を残している
さらに女性の服も混色の緑なので自然
静物にもはや色を塗らない
フォルマリズムの走り?36, 34含め
37赤い家的に構図が本格的に壊れ始めた上、原色的
ヤシの木やジグザグ、原色がエスニック、ラテン風
インドのカーテン布の伏線…?
版画イスラム
やはりスペインの文化もバカにならない
57, 63一見なんだかわからない
圧倒的な省略
リトグラフなどは版画、印刷として書籍化、教科書化にもってこいか
本の表紙は楽譜にそっくり
伝統的な教科書形式か
壁画は壁画としてシンプルながら洒落ていていい
大きいものにはシンプルな方がわかりやすい
アンリ・マティス《森の中のニンフ(木々の緑)》1935-1943年
油彩/カンヴァス、245.5 × 195.5 cm、オルセー美術館蔵(ニース市マティス美術館寄託)
© Succession H. Matisse Photo: François Fernandez
83ニンフらの像は曖昧
二次元の中において、残像のように動きを表したかったようにも見える
sec3.5
1940s
ストリート系チックにもみえる
バスキア?
原色やサンゴの曲線
sec4
アンリ・マティス《ブルー・ヌード IV》1952年
切り紙絵、103 × 74cm、オルセー美術館蔵(ニース市マティス美術館寄託)
© Succession H. Matisse Photo: François Fernandez
92案外青の色味に違いあり
重ね合わせ
微調整なのかそれ含め表現か
切り絵だけなら切り出しを試行錯誤すれば…

94結局物理的な表現も手か
所詮サイン波だが
花束といいつつ花よりも茎葉が目立つ形態
アンリ・マティス《花と果実》1952-1953年
切り紙絵、410 × 870 cm、ニース市マティス美術館蔵
© Succession H. Matisse Photo: François Fernandez
切り絵の配置の本質的自由さ
依頼主のアメリカの国土風土
戦後の時代感
いずれもが自由を進める雰囲気で生き生きノビノビ爽やか

修正してもなお美術足り得る評価、本質
結果的に衣装デザインは型紙にもなった?!
舞台の服飾デザイン経験も生きたか
意図的に(なほどに)微妙にアシンメトリーだし型崩れ
ロマネスク…?
海藻や植物のモチーフをリスペクトした?

アンリ・マティス《白色のカズラ(上祭服)のためのマケット(正面)》
1950-1952年、切り紙絵、126.5 × 196.5 cm、ニース市マティス美術館蔵
© Succession H. Matisse Photo: François Fernandez




![推しエコノミー 「仮想一等地」が変えるエンタメの未来 [ 中山 淳雄 ] 推しエコノミー 「仮想一等地」が変えるエンタメの未来 [ 中山 淳雄 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0357/9784296000357_1_3.jpg?_ex=128x128)